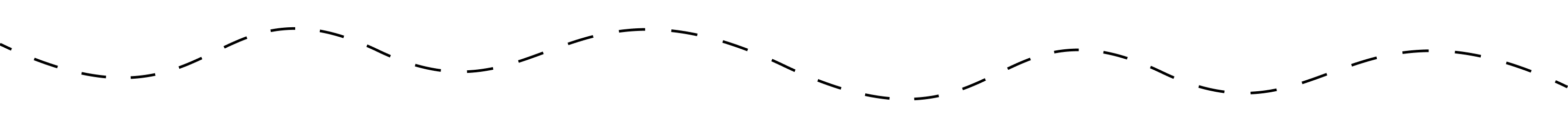
3. ひとつずつ越えていく道のり
先日ある動画を見ていて、そこから伝わる動画発信者の方の集大成の中の一つのコンテンツに込められた思いが痛く伝わってきたことから、こちらの著作物の中の文章をふと思い出し、引っ張り出してきました。
人生の道程での夢に対する’小さな達成感の積み重ね’の大切さというものにご興味をもたれましたら引き続きお読みください。

お伝えしたい内容を、この度AI要約しました
(簡潔に短く的確に伝えることが苦手なaonaが、思い切ってAIにお願いしました)
*今後、このサイトにおいて、はっきりとAI要約しているものについては、このように明示させていただこうと考えます。
高すぎる目標を持つと、逆に挫折しやすくなるが、低い目標を持つと達成感が得られます。達成感は大切で、小さな目標を立てて実践することが目標達成のコツでもあります。少しずつ高い目標に挑戦していくことで、プラス思考が生まれ、目標を達成しやすくなるでしょう。本文をAI要約による
次々に小さな目標を立てて実践していくのが、目標達成のコツといえるだろう。
著書 ザ・フナイ 2016年2月号 Vol.100 時代の変わり目に立つ我々の役割 より
236頁 上段12行目より引用
生きるための原動力にもなることのひとつが夢をもつことですが、うまく夢さえ描けられるのか、もしかすると、夢を掲げることがひとつの目標となる場合もありかもしれません。
着地地点が確実にあるのかわからない中で奮闘していくことは勇気がいるかもしれませんが、やらなければ止まる、逆に、やれば何かしらに道が広がるかもしれず、少しずつ・・・と捉えていくとプラスになっていくものかもしれません。
2.土づくり投稿から繋がった場所
京都南部は城南宮さんが発行されている’源氏物語の庭(草木の栞)’をご紹介したいと思います。
著書 源氏物語の庭 草木の栞 理学博士 廣江美之助著 発行所 城南宮
冊子は男性の手の平サイズで1㎝ほどの厚みです。このページの1番でご紹介しました’萬葉の花’の冊子に似た構成になっています。
万葉集は奈良時代のものです。源氏物語は平安時代に生まれた古典文学ですが、その中でもこちらの著は、物語の背景の植物描写に視点をおいてあり、谷崎潤一郎新訳の源氏物語を引用されたものだとあります。
なるほど、源氏物語を深く楽しみたいものにとっては、物語が奥行を増すための資料となるのかもしれません。
aonaは正直に源氏物語を読み耽ったことがあるかといえば無いですが、単純に植物が好きということから、こちらの著書を手にとらせていただきました。
それが、植物について和歌を筆頭に本当に詳細に丁寧に記されていて、植物の掲載写真も鮮明で、大変面白いです。昔は柏の葉でつくった箱が食物を入れる器だったなどの画像や、興味深いものが載っています。たしかに実家の自生でも利用しますが、器の代わりに今でもバランの葉を洗って食材を飾ったりしますよね。
物語に出てくる人物がまとう着物の染色なども、色の説明もあります。貴重な資料と思います。
城南宮さんのご神苑(源氏物語花の庭)は、思った以上に広いです。



歩いていてご庭園管理の細やかさが本当に伝わってくるのです。
と、こんなふうに語ることのできる人間ではありませんが、素晴らしいと思います。
梅の時期にはパッと明るくなったご神苑を、冬から春の間には儚く開く椿の花を十分に楽しめて、ハイキング、広いお庭で足腰も健康になりそうです。
1,aona-3tの名前の由来のひとつとなった和歌
植物にまつわる万葉集が一冊になった古本から、あをなの一歌です。
すごも敷きあをな煮持ち来梁にむかばき懸けて息む(やすむ)此の君 (16・三八二五)
萬葉の花 著者 松田修 株式会社 芸艸堂 昭和32年4月24日 発行
著者は山形県に生まれ、東大農学部卒、1953年に副会長として社団法人植物友の会(現在は公益社団法人さんとして活動されているようです)を発足されるなど植物文学の研究家として知られる。
植物に興味をお持ちの方を対象に、発足した社団法人の植物愛好団体です。
公益社団法人植物友の会 HP より抜粋
「植物から学ぶ」をモットーに、自然を通して植物が生き残るための巧妙な知恵やしくみ、植物の種類の見分け方、植物に関する様々のことを、多くの方々に啓蒙するための会です。植物に少しでも興味を持っておられる方なら、どなたでも入会できます。
歌の説明
アヲナは現在では菜類の総称ですが、もともとはかぶらのことだそうです。「和名本草」にもそのように記されているとあります。
梁のうえにじか足袋をかけて休んでいるお方に、薦敷を敷いて青菜の煮たものをお出ししてあげましょう。といった感じの歌になります。
aonaは、和歌の季語や成り立ちなどの歌を詠む為の構成ではなく、単純に歌を聴いたときに思い浮かぶ背景のようなものを感じることが楽しく思います。こちらの歌はなんとなく、その昔々の日本の日常風景といった印象として受けています。現在でも皆さんが持ち合わせるような心情ではないでしょうか。温かいですね。
それではこの辺で。ありがとうございました。